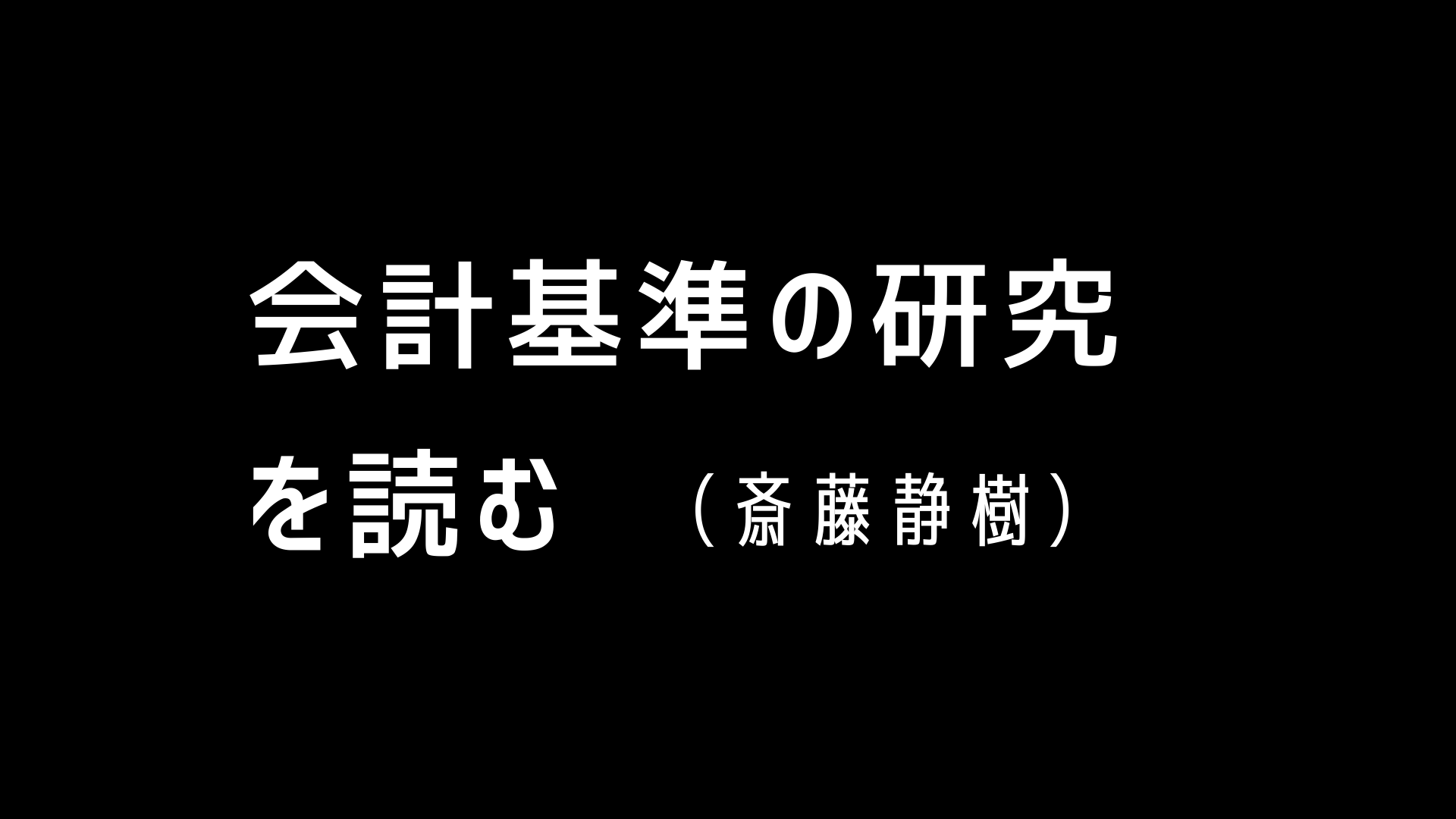|
|
第5章 経済的所得と会計上の利益
はじめに
経済的所得と会計上の利益(特に純利益)の関係をみていきます。
古典的な経済的所得の概念では、一般に個人の所得が想定され、企業というより、株主の所得に近く、また、新古典派経済学では、企業と株主を区別して、それぞれ別の勘定を持つ関係を想定する必要はありません。
企業会計の分野でも、経済的所得の概念はしばしば話題になっており、大きく2通りの議論があります。
一つは、会計上の「あるべき」利益概念を模索する上で規範的に使う試みで、真実利益(true income)アプローチなどと呼ばれています。(1960年代にビーバーにより総括)
もう一つは、会計上の利益概念を解明する上で基準点として使う試みで、記述的なアプローチです。本書ではこちらの観点で経済的所得をみていきます。
所得の基本概念と近似概念
ヒックスの所得第1号
ある期間に消費してもなお期末において期首と同じように裕福(well off)であることを期待できる最大値 ≒ 期首の資本価値を期末に維持した余剰
ヒックスの所得第2号
単なる資本価値の増分ではなく、当期に消費でき、しかも次期以降の将来に同じ額を消費できると期待される最大額
毎期、同額の期待の変化、価値変動が起きることは期待できません。
⇒ヒックスの所得第2号は、期首と期末の資本価値差額から期待の変化に伴って生じた価値変動分(期待外の利得;ウィンドフォール)を除いた額
事前の所得 income ex ante
Y ante = (V1-V0)-{V1-E0(V1)期待の変化} = E0(V1)-V0(事前の期待=事前の所得)
事後の所得 income ex post
Y post = (V1-V0)-{E1(V0)-V0 期待の遡及修正} = V1-E1(V0)(実現値ではなく事後に計算する期首の期待値=事後の所得)
*E1(V0);過去を振り返って推定した仮想的な hindsight value
E1(V0)-V0;期末の情報がなかったためのウィンドフォール
期待の変化が期末に起きた場合
期首100ドル;毎期の期待5ドル、長期利子率5%
期末120ドル+当期の実績6ドル;翌期から毎期6ドルの収入に期待変化、長期利子率5%
| 事前の所得 | 事後の所得 | |
| ヒックスの所得第1号 | 5ドル | 26ドル |
| ヒックスの所得第2号 | 5ドル | 6ドル |
期待の変化が期首にわかっている場合
期首119ドル;当期の期待5ドル、翌期の期待6ドル、長期利子率5%
期末120ドル+当期の実績5ドル;長期利子率5%
| 事前の所得 | 事後の所得 | |
| ヒックスの所得第1号 | 6ドル | 6ドル |
| ヒックスの所得第2号 | 5ドル | 5ドル |
行為(conduct)にとってレリバントな所得は、常にウィンドフォール・ゲインを除外していなければならない
ヒックス
所得とウィンドフォール
所得から除かれたウィンドフォールはどこへいくのか?
新たな期待は、時期以降の収入として実現し、実際の現金収入に置き換わります。
新たな期待から生み出される「実際の現金収入」は実現しますが、「ウィンドフォールの現在価値」は、無限の期間で考えると経済的所得から除かれたままです。
では、企業会計の利益(純利益)ではどうでしょうか?
期首に期待されなかった資本価値の変動(=事前の所得No.2)は、
①期中に生じた実際の収入が期首の期待と違った分
②期末から先の将来に関する期末時点の期待が期首時点のそれと違った分
の両方が含まれます。
*事前の所得、事後の所得、ヒックスの所得第1号、第2号のうち、事前の所得第2号の場合
事前の所得No.2ではウィンドフォールとしてすべて所得から除きますが、企業会計の利益では、外貨建債権債務に係る為替差損益など、現金と同等で、自由に換金・決済できる市場があり、換金・決済に事業上の制約のない金融資産負債に係るウィンドフォールは純利益に含めます。
ウィンドフォールをすべて除く「経済的所得」に対して、一部を含む「企業会計の利益」では、ウィンドフォールを、どこで、どこまで含めるのか、基本原理があるはずです。
事前の所得No.2
事前の所得、事後の所得、ヒックスの所得第1号、第2号のうち、事前の所得第2号が経済的所得の代表のように取り上げられています。
これは、事後の所得No.1をベースとした資産負債アプローチ(IASB等の見解)に対し、経済的所得の観点から包括利益など企業会計の利益を検討するには、事前の所得No.2をベースとすべきである(斎藤先生の立場。その結果、原則としてウィンドフォールを除く収益費用アプローチが支持される)、という議論を踏まえてのことだと思われます。
参考:包括利益と経済的所得の中心概念(勝尾裕子)
『学習院大学 経済論集』第57巻 第1・2合併号(2020年8月)
Variable Income の概念
米国会計士協会(AAA;米国公認会計士協会AICPAの前身)は、1940年代後半からロックフェラー財団の援助で進めた企業所得の概念についての1952年の最終報告書に先立ち、1950年に「企業所得に関するモノグラフ」を刊行しました。
その冒頭のアレクサンダーの論稿で、新たな概念“Variable Income”が提示されました。
将来の期待収入に影響しない、現金ないし現金同等物の収入に確定した、期待外の要素は、経済的所得から除かれても、Variable Incomeでは含めます。
Variable Incomeは、投資プロジェクトを通算した所得が正味の収入に等しくなる(キャッシュフローが所得流列の拠り所になる)という制約を経済的所得に加えたものです。
経済的所得(事前の所得No.2)は、単なる資本価値の増分ではなく、ウィンドフォールを除いた概念であり、Variable Incomeはそれがキャッシュフローとして確定するときに所得に含める概念です。
第6章 概念フレームワークと利益概念
概念フレームワーク
1989年版フレームワーク
2010年版フレームワーク
2018年版フレームワーク
質的特性
よくわかる「IASB概念フレームワーク」シリーズ 第2回(Deloitte)
『有用な情報は、目的適合性があり、財務情報の実質を忠実に表現するものでなければならない』
基本的質的特性
・目的適合性 Relevance
・忠実な表現 Faithful representation
*1989年版フレームワークで「信頼性 reliability」と呼ばれていたもの。
「信頼性」は人によってさまざまに解釈され混乱を招いていたため、2010年版で改訂された。
補強的質的特性
・比較可能性 Comparability
・検証可能性 Verifiability
・適時性 Timeliness
・理解可能性 Understandability
コスト制約 Cost constraint
投資家の企業評価と利益情報
財務報告の目的は、「投資家の意思決定に有用な情報を与えること」です。
質的特性は、目的適合性(レリバンス)と忠実な表現です。
レリバンスについて、
投資家の意思決定との関連性から考えられる、もっとも厳密な検証に耐える解釈としては、情報経済学的な意味での「情報価値の存在」です。
つまり、追加情報が利用者の意思決定を変えるときの、限界的なペイオフの増分をその情報の価値(粗価値)とみる解釈です。
=特定の会計情報が、均衡株価や投資リターンの変化をどこまで説明できるか?
という定量的な実証作業
投資情報としての企業成果は、キャッシュフローを期間配分した純利益を、恒久利益の近似値としています。さらに、事業価値の評価には、事業成果との関連性が高い営業利益の方が純利益より有用です。
概念の定義と情報の有用性
かつて資産・負債アプローチから収益・費用アプローチへパラダイムシフトが起きました。(1920-30)そして、今(1980-)、収益・費用アプローチから資産・負債アプローチへパラダイムシフトが起きています。
その二つの流れとも、「直接金融の拡大に伴う投資家の情報ニーズ」を理由としています。
同じ理由で正反対の動きが起きているのでは、無定見な議論の結果とも見えます。
ここで、「概念の定義」と「情報の価値」の切り口から、
かつては、「情報の価値」の面で資産・負債アプローチから収益・費用アプローチへ重点が移行し、今は、「概念の定義」を整備するために収益・費用アプローチから資産・負債アプローチへ重点が移行している、と理解すればそれなりに首尾一貫した思想がある、と考えられます。
自己創設のれんとバランスシート
自己創設のれんの資産性(貸借対照表能力)は企業会計の最大の難問です。
自己創設のれんとは?
企業買収をした時、資産負債を時価評価した後、対価と純資産の差額がのれんになります。
企業買収ではなく、自社について、対価を時価総額に置き換えて考えると、時価総額と純資産の差額は、自分で作り出したという意味で自己創設のれんといいます。
一般に、超過リターンは新規参入者との市場競争によって有限期間で消滅するので、企業は常に投資をしながら新たなのれん価値を形成する必要があります。
有限期間で消滅するものなので、償却するのが整合的です。
(自己創設のれんBS計上しない=現状)
① 投資家が過去の投資結果を会計情報で検討する
② 投資家が将来の投資結果を予測して投資する
⇒ 時価総額が決まる(自己創設のれんは株式市場で観測できる)
(自己創設のれんをBS計上した場合=仮定)
時価総額からBS作成(=会計情報)
⇒ 投資家は自分たちの予測の結果を知るだけとなり、会計情報に意味はなくなる
第7章 会計基準の形成と統合
完全な情報をもつ市場参加者を想定した古典的な経済学では、情報開示は、社会的弱者の保護の観点からとらえられることが多かったようです。
経営者と投資家の双方にある誘因をみていきましょう。
情報開示の私的誘因と公的規制
情報開示(ディスクロージャー制度や会計基準)は、情報に乏しい投資家を保護する目的で、経営者に開示を強制する公的規制とみられてきました。
しかし、投資家が情報劣位のままに置かれた場合、発行市場において株式や債券の引受価格を引き下げえることになりますので、いわば市場価格で保護されているといえます。
そうすると、経営者には、内部情報を投資家に伝えて彼らの保守的なリスク評価を緩和し、資金調達コストを引き下げようとする誘因が生じることになります。
情報開示には私的誘因があるといえます。
ただし、資本市場、経営者市場が十分に競争的でない、独占的市場のケースでは、情報開示のインセンティブが十分には働かないので、公的規制が必要になります。
私的情報の品質保証と会計基準
資本市場、経営者市場が競争的であれば、公的規制で情報開示を強制しなくても、情報開示にインセンティブが働きますが、個別のケースになると、不利な事実は隠そうとします。
会計基準は、経営者の自主開示の誘因を利用して意思決定に有用な情報を引き出しつつ、自己申告に伴うバイアスを排除する工夫といえます。
私的契約の不完備性と会計基準
社会規範としての会計基準は、同時に市場取引における私的な契約条件の標準書式であり、フォーマットの共有により取引コストの節約が期待されるものでもあります。
契約の内容が不十分であるために効率性も不十分になってしまうことを「契約の不完備性」といいますが、会計基準への公的機関の関与は、この「契約の不完備性」を公的規制で補完するという意味があります。
会計基準の形成と基準間競争
会計基準の共通ルール(一つの会計基準の中でのルールの集約)を生み出すのは、市場参加者の選択となります。
複数の会計基準間の標準化や統合化も、市場参加者の選択により、不十分でも過度でもない最適なレベルで行われるのが理想です。
「グローバルな資本市場が相互に基準を承認し、複数のメニューを用意して選択をそれぞれの市場の裁定に委ねるやり方が模索されている」
とありますが、国際会計基準と米国基準以外は収斂されているのが現状なので、この現状認識は違和感があります。(出版は2009年(増補2010年版)です)
私的な契約条件の標準書式として集約されてきた会計基準に対し、公的規制を行うことは、規制や制度の本質をめぐる「公と私」の対立として論じられることが多いです。
上記のように市場の力(市場参加者の選択)でうまくいく、という考えに対しては、会計基準も強者を抑えて弱者を保護する社会正義の観点から理解されるべきで、強者と弱者の対等な取引を考えても意味がない、という批判もあるようです。
会計基準の画一化と企業統治
代替的なルールを削減し、経営者に操作の余地を与えないことが透明な情報開示になるというのは、ある意味では一つの神話に過ぎません。自主規制に対する不信と強行法規への期待が画一的な開示規制に直結しているかもしれませんが、企業統治もまた基本的には市場を通じたステイク・ホルダーの監視に待つべき問題です。
企業のガバナンスを強化する上で、情報開示の質を高めることが重要ですが、それは、情報開示を通じて市場の監視が強まるからです。開示制度への期待は、その意味で市場の監視機能に対する信頼でもあります。
会計基準の設定も国際的な基準の統合も、市場に任せ、選択肢を持たせて競争させるべきです。
第8章 企業会計と配当規制
会計情報は、投資家以外にも利用されます。その代表例は債権者です。
債権価値の希薄化を避けるため株主への配当を制限する契約や制度では、会計情報が利用されてきました。株主への配当は、元手となる資本を除いた、余剰としての利益(留保利益)に限ることが一般的です。
会計上の利益と配当財源
資本も留保利益も株主のものなので、配当を留保利益に限定することに、株主にとっては意味はありません。資本コストを上回る投資収益が得られるかどうかにかかっています。留保利益でも資本でも余分であれば株主に返した方が資本コストをより超過した投資収益になります。
債権者保護を目的に、会社法制や社債契約では、元手となる、維持すべき資本価値を決めて、それを超える利益を配当限度としています。
会社法では、拠出資本部分の払い戻しには、厳格な債権者保護手続きが必要となります。
この章では、余裕資金で運用されている、現金の流入を伴わない、金融投資の時価評価益を配当することについて検討していきます。
売買目的有価証券の含み益
売買目的有価証券の値上がりで利益を計上し、その分を配当することを考えます。
実際に値上がりした分を切り売りして配当すれば、債権者から見て企業資産のリスクに変化はありません。そうではなく、そのまま保有を継続したらどうでしょうか?
増資で配当資金を調達した場合は、株主間で資金を回しているだけで企業資産のリスクに変化はありません。
借入で配当資金を調達した場合は、有価証券が、値上がりした有価証券と値上がり分に相当する借入金との組合せに変わってしまっています。資産価値は同じでも裏付けとなる資産負債の要素は、よりリスクが高くなった可能性があります。資産代替です。
新規の借入による債権価値の希薄化が含み益をめぐる規制の中心的な論点となります。
含み益の配当と資産代替
資産の含み益について、資産は継続保有し、新規の借入により資金調達して配当する場合、株主持分に対する負債の比率が上昇します。負債比率の上昇が債権のリスクを高めれば、それに伴う債権価値の下落は株主持分の価値を同じ額だけ引き上げます。その分の企業価値は債権者から株主へ移転されます。
「新規借入で資産を購入した場合、株主持分に対して負債比率が上昇し債権価値が下落し株主持分が増加する」ということが一般的にいえる、なので含み益の配当についてもいえる、という理解でいいのでしょうか。
配当制限のルールと考え方
日本では、売買目的有価証券の含み益が利益となり剰余金となった場合、配当に制約はありません。ただし、剰余金にならない評価差額(その他有価証券評価差額金)については、評価差益は分配可能額に含まれませんが、評価差損は含めます。分配可能額の算定 by EY
また、2001年の改正商法では、債権者保護手続を伴って行われる、資本金の減資差益や法定準備金の減少差益について配当は制限されません。配当の可否を株主の払込資本か未分配の利益かという、いわば源泉に依拠させてきた旧来の観点を整理し、まず債権者保護手続を経ているかどうかで判断するという、より包括的な原則を明示したといえるかもしれません。
米国では、会社法の配当規制は緩やかですが、社債契約では制限することが多く、
・会社のプロジェクトをリスクの高いものに入れ替える事業政策(資産代替)を直接規制する
・短期の保有株式の評価は開示のための会計基準とは別に低価法が適用され、含み益の配当が債権者との契約で禁止される
といったこともあるそうです。
おわりに
2005年、旧商法第32条2項の包括規定「商業帳簿ノ作成ニ関スル規定ノ解釈ニ付テハ公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ」は、
会社法第431条「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする」
と改められ、斟酌するものから従うものになり、会計慣行の規範性は高まりました。
国際会計基準では、投資不動産は公正価値による評価と損益認識がルール化されており、日本で導入することになった場合、不動産の含み益の配当が債権価値の希薄化を招く点についてどう整理するのか、難しい問題です。
|
|