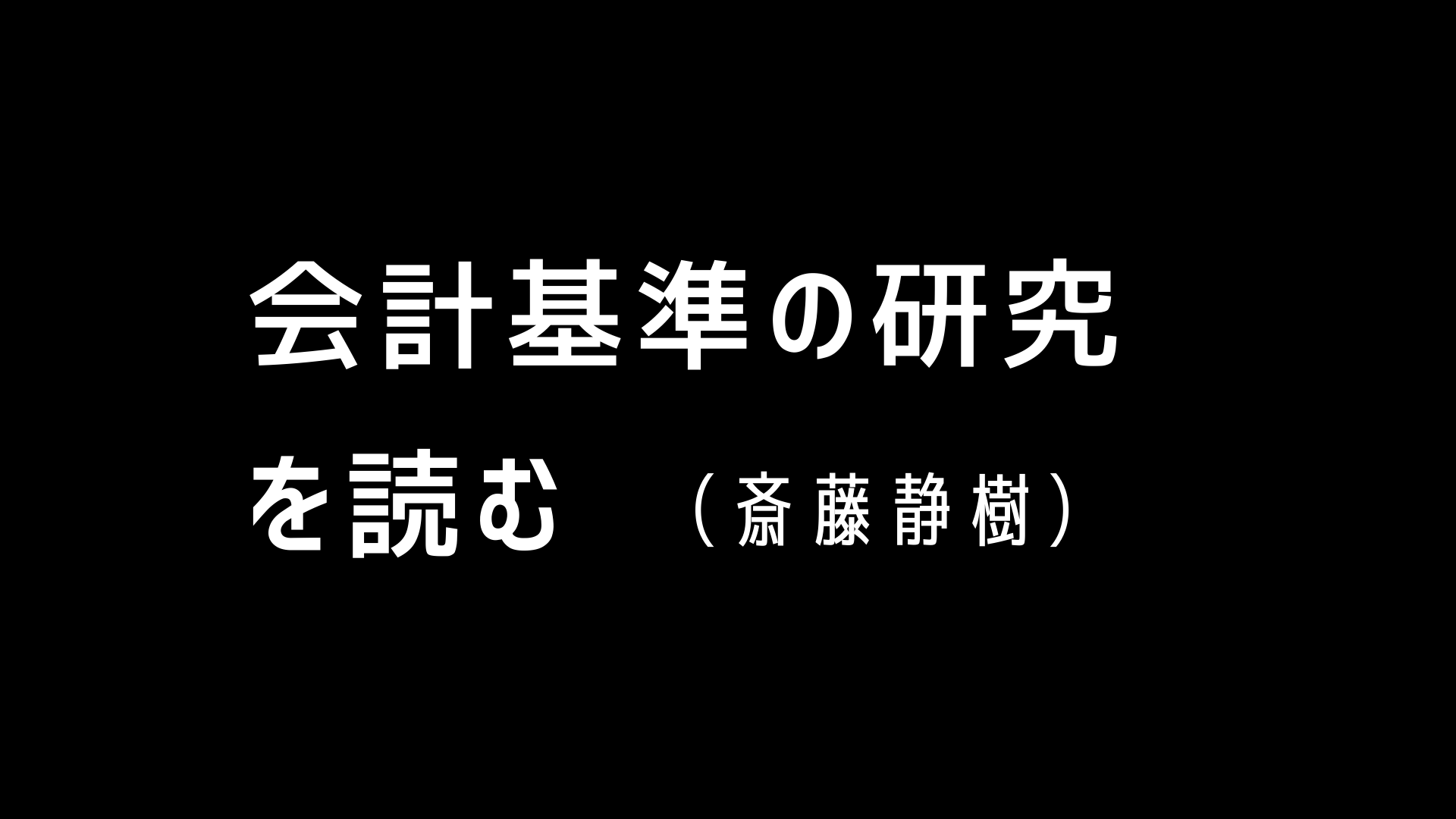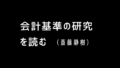第13章 事業投資と収益認識
現在、収益・費用アプローチから資産・負債アプローチへパラダイムシフトが起きています。収益認識についても、稼得過程を要件とせず、資産と負債が決まれば測定値までがそのまま決まるような、資産・負債アプローチによって一元的に処理する方向に進んでいます。
営業利益と保有利益
資産の評価に基づく利益の測定を提示したのは、エドワーズ・ベルのモデルです。
伝統的な利益概念では、販売まで購入価格で評価します。
実現可能利益は、生産までは再調達コスト、生産した時点で販売価格で評価します。
事業利益は、販売まで再調達コストで評価します。
実現可能利益は、資産の継続保有の意思決定に適合し、事業利益は、事業継続の意思決定に適合する、とされました。
実現可能利益は、資産・負債アプローチによる収益認識ともいえますが、収益認識を稼得過程から切り離して資産評価に一元化する試みは否定されています。
工事契約における進行基準
エドワーズ・ベルの実現可能利益モデルは、資産・負債アプローチを機械的に収益認識に適用したといえます。エドワーズ・ベルは、また、保有資産の価値増分より、リスク開放*1による収益認識の方が目的適合性(レリバンス)が高いことが概念的考察*2により示しています。
*1討議資料「概念フレームワーク」での表現。「収益認識に関する会計基準」では「履行義務の充足」となっています
*2目的適合性は最終的には実証(株価と有意な相関があるか調べること)により確かめられます
長期の請負工事については、工事進行基準が定着しています。契約時に一括して認識しないのは、履行にリスクがあるからではなく、費用が発生した後に販売基準が適用される通常の例と異なり費用が販売契約の後に発生するため、費用総額にリスクがあるからです。
契約資産の概念と収益認識
収益認識は、稼得ないし実現(討議資料「概念フレームワーク」では投資のリスクからの解放)から「履行義務の充足」となりました。これは、契約資産(契約上の権利)と契約負債(契約上の義務)を認識、その増減から収益を定義しようとする、資産・負債アプローチからの収益認識といえます。⇒収益費用対応の原則の否定
ただし、契約と同時に契約資産が認識、収益が計上されると、自己創設のれんが計上されることになります。それは避けるようになっており、概念上は資産負債から収益が定義されているものの、従来と同じことを表現だけ変えている面はあります。
第14章 減価償却と価値減耗
経済的所得と資本の価値減耗
期待の変化のない、ウィンドフォールのない状態を想定します。
各期のキャッシュフローを\(C_n\)、資本コストを\(r\)、資本設備の価値を\(V\)とすると、
\(V_0=\sum_{i=1}^{n}C_i(1+r)^{-i}\)
\(V_1=\sum_{i=2}^{n}C_i(1+r)^{-i+1}\)
\(D_1=V_0-V_1=C_1-rV_0\)
となります。
3期で確認します
\(V_0=\frac{C_1}{1+r}+\frac{C_2}{(1+r)^2}+\frac{C_3}{(1+r)^3}\)
\(V_1=\hspace{15mm} \frac{C_2}{1+r}+\frac{C_3}{(1+r)^2}\)
\(\quad =\hspace{15mm} \frac{C_2(1+r)}{(1+r)^2}+\frac{C_3(1+r)}{(1+r)^3}\)
\(V_0-V_1=\frac{C_1}{1+r}-\frac{rC_2}{(1+r)^2}-\frac{rC_3}{(1+r)^3}\)
\(\hspace{15mm}=\frac{(1+r)C_1-rC_1}{1+r}-\frac{rC_2}{(1+r)^2}-\frac{rC_3}{(1+r)^3}\)
\(\hspace{15mm}=C_1-rV_0\) 時の経過に伴う増分
第1期の成果\(Y_1\)は、
\(Y_1=(C_1-Y_1)-V_0=C_1-(V_0-V_1)=C_1-D_1=rV_0\)
となり、正味の成果は、期首資本設備に資本コストをかけた利子の額になっています。
もっと単純に、正味のキャッシュフローが毎期一定\(C_i=C\)とすると、
第1期の価値減耗は
\(D_1=V_0 – V_1=C(1+r)^{-n}\)
となります。
3期で確認します
\(V_0=\frac{C}{1+r}+\frac{C}{(1+r)^2}+\frac{C}{(1+r)^3}\)
\(V_1=\frac{C}{1+r}+\frac{C}{(1+r)^2}\)
\(V_0 – V_1 = C(1+r)^{-3}\)
価値減耗額は、毎期、逓増します。
企業会計における減価償却
企業会計の減価償却では、各期に配分される費用は資本設備購入額\(K_0\)であり、自己創設のれんを含む資本価値\(V_0\)ではありません。つまり、各期へ配分する費用の総額が経済的な概念(資本設備の価値減耗)と異なりますので、その配分も価値減耗の経路と異なることになります。
資本設備の価値ではなく、潜在的な用役の減耗が費用配分の基礎となり、各期の収益動向に依存しない、定額法が実務に定着しています。定額法のほか、収益性の低下を考慮した加速償却も一部で採用されています。
価値減耗が成果によって決まるのに対して、減価償却は、成果に依存した一種の「利益償却」を否定、つまり「利益処分性」を否定した概念であり、利益から控除される費用としての地位を確立してきたといえます。
時価ベースの減価償却
経済的な価値減耗と取得原価ベースの減価償却との差は、期首の評価替と期末の評価替との正味となり、時価ベースの減価償却との差は、期首の評価替から期中の減少分を控除した正味となります。
取得原価ベースと時価ベースのどちらを採用すれば経済的所得に近くなるか、は決められません。
会計学の研究者が経済的所得に言及してきたのは、会計のルールが持つ特性を分析し記述するための道具としてであって、会計上の利益を経済的所得に近づけることが望ましいとはいえません。
第15章 事業用資産の減損
減損損失は、経済価値が簿価を下回ったときだけ認識する、上下非対称な保守的評価で、資産価値を開示するというより、資産計上額を将来CFで回収できる範囲に限定するという趣旨です。
事業用資産と会計上の評価
事業用資産の価値は、将来CFを資本コストで割り引いた現在価値です。
資産価値を開示する、ということなら、金融投資は時価、事業投資は現在価値となります。
しかしながら、企業価値の評価は投資家が自己の責任で果たす固有の役割ですので、経営者が評価するのはおかしな話です。ディスクロージャー制度に求められる役割は、投資家が企業の価値を評価するのに役立つ情報を市場に伝えることで、経営者が自ら評価した企業価値を投資家に教えることではありません。
会計と市場との役割分担は、事業用資産の評価に通常は時価も現在価値も使わない実務を定着させてきました。
収益性の低下と事業用資産の減損
物理的な損傷や減耗はともかくとして、将来CFの予想の変化、期待の変化による収益性の低下を事実に先立って認識するのは、実現とかリスクからの解放という考え方とどこまで整合するのでしょうか。
保守主義の理念も、損失を先取りした簿価切下げの根拠までは説明できません。CFが生じなければ、本来は利益も損失も実現しないはずです。
減損を将来の損失の先取りとみるのではなく、あくまでも現在の損失とするためには、収益性の低下に伴う資産価値の下落を、そのまま当期の損失として性格づける理屈が必要です。
また、減損が収益性の低下に起因する資産価値の下落を意味するのであれば、簿価の回収可能性はそのテストになるのでしょうか。
事前に決められた減価償却のスケジュールよりもCFの回収が早く進むケースでは、収益性が当初通りでも、取得原価を上回っていた資産価値の減耗が、減価償却による取得原価の減額を追い越して簿価を下回ることもあります。
減損の懸念:簿価の回収と投資の回収
資産価値が償却後の簿価を下回るケースには、収益性の変化とは関係なく、キャッシュフローが早い期間に集中しているだけのことがあります。これは、定率法でも起きる可能性があります。
減価償却のスケジュールでは「簿価が資産価値を下回る」工夫はされていません。
簿価が将来に回収を見込める額に比べて過大でも、すべて収益性の低下が原因として、当期の減損とすることには無理があります。当期の損失というより、過去の減価償却を新たな情報に基づいて修正した方がよい場合もあります。ある時点の簿価を基準に、回収不能な分をすべて減損による損失とするのは、測定の便宜はともかく概念上は疑問があります。
収益性の低下を資産価値の評価に結び付けて現在の利益に負担させるには、当期に生じた事実で説明できなければなりません。
資産の取得後に資産価値が低下していれば収益性は低下したといえますが、本来、減損といえるのは、それが取得価額を下回って、もはや投資額の回収を見込めなくなったケースだけのはずです。
簿価ではなく、取得価額を下回った場合の処理であれば、減損は事後に判明した負ののれんの計上(=取得原価からの控除)といえます。
このように、将来だけでなく、過年度も含む投資期間を通じた投資額の回収可能性という観点は、ある時点の簿価の、その後の回収可能性という観点に比べると、実現利益の概念と整合します。それは、投資額のうち、もはや成果を生まないことが確定したという意味で、リスクから解放された部分といえます。
回収不能と判明した過剰投資の切捨てという、上記の概念で処理すると、取得時に戻り、取得価額を切り下げ、従来の償却パターンで償却をやり直した結果が減損後の簿価になります。
減損の測定と過年度減価償却
簿価が回収可能額を超えるというだけなら、収益性が低下していなくても、キャッシュフローのタイミングと減価償却のスケジュールとの関係によって生じてしまうことがあり、その分の簿価の修正は、本来の減損と区別した方が望ましいです。
減損の測定と減損後の利益
会計情報の利用者から減損をみたときは、
・資産の収益性が低下して超過リターンが望めなくなったこと
・資産を処分していないので資本コストに見合うフェア・リターンは期待できる
という解釈になります。
おわりに
のれんに限らず事業用資産のすべてを減損処理に一元化すればよい、という極論も、そこまでいけば、減損という下方のみの評価替に限らず、切り上げも含めた公正価値会計という話になりますが、それは、資本市場が作り上げてきた開示制度の歴史を、すべて清算して1世紀ほど昔に後戻りさせるだけともいえます。